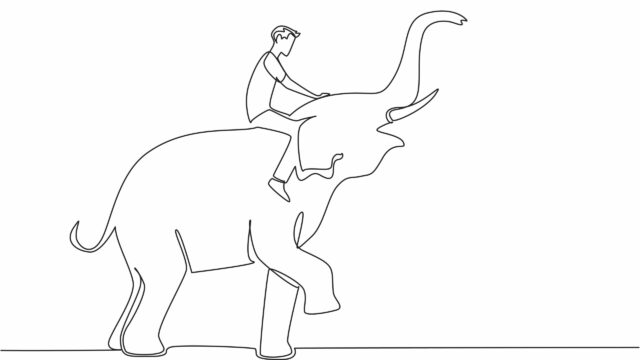どうも!ちゃろです!
今回は名著『完訳 7つの習慣-人格主義の回復-』を読んでみたのでポイントをまとめていきます。
言わずと知れた世界的な自己啓発の名著であり、やはり多くの人に読まれているだけあって内容も読んでいて発見が多いです。
私たちができていそうでできていない人間関係や人生を充実させる考え方が満載となっています。
そんな読んで人生が変わるかもしれない本書のポイントをまとめていきます。
7つの習慣とは
本書いてコヴィー博士が提唱した『7つの習慣』は以下の通り
- 主体的である
- 終わりを思い描くことから始める
- 最優先事項を優先する
- Win-Winを考える
- まず理解に徹し、そして理解される
- シナジーを創り出す
- 刃を研ぐ
それぞれ詳しくみていきます。
主体的である
第1の習慣は『主体的である』です。
私たちは日々多くの選択をしながら生活していますが、その選択をどれくらい自分の意志によって選択しているか意識している人は少ないように思います。
些細な行動や決断を感情的な反応でなんとなく選んでしまったり、他の人に言われたからと受け身になるのではなく、自らの意志で立ち振る舞いを選択することが必要です。
そして、現在の私たちの性格や行動は過去の選択の積み重ねの結果であり、他人や社会など周りの環境のせいにしてはいけません。
何か嫌なことがあったとしても、間違いなく過去にそうなることを防ぐ何かができたはずなのに、防ぐための行動をしないことを選択したのは自分自身であったと認識し、自分の責任であることを前提に行動していくことが重要です。
この習慣について私は、人生における選択は自分で選んでいて環境によって選択肢が狭まっていたとしても自分が納得して最善を選んできているという意識があります。
ただし、主体的であることと自分本位であることを間違えてしまっている時があるようにも感じるのでそこは改善していきたいです。
例えば新しく何かを始める時に、自分の考えや思いを優先するあまり学んだことや教わったことからの吸収が阻害されてしまっているといったイメージです。
選択は自身の強い意志で、学ぶときは素直に柔軟にを心がけたいです。
終わりを思い描くことから始める
第2の習慣は『終わりを思い描くことから始める』です。
人生には必ずゴール(終わり)があり、かつそのゴールは人それぞれなので自分で設定する必要があります。
終わりを設定せずに進んで行こうとすると必要のないことに時間を取られてしまったり、まわり道になってしまいます。
何のために行動するのかという自分の軸をはっきりさせ、ブレない生き方をするために自分が大切にする原則(定義)を決め、それに沿った行動を心がけましょう。
個人的には、目標を決めて何かを成し遂げようと思った時には達成のためにやることを考えるのと同じくらいやらないこと(今の生活の中からやめること)を考えることが大切だと感じています。
時間(命)は有限なのでしっかりとゴールを決めて、進んでいきたいですね!
最優先事項を優先する
第3の習慣は『最優先事項を優先する』です。
一口に「最優先事項を優先する」といっても、そんなことは当たり前のことだと思ってしまいがちですが、実は多くの人ができていないことだとされています。
私の経験上これはいわゆる「手段が目的になっている」と表すとわかりやすいかと思います。
例えば部屋や職場を掃除をする時、目的はあくまでその場所をキレイにすることであるはずですが、多くの人は一通りの拭き掃除や掃き掃除をささっとやってしまいます。
細かい汚れなどが残っている状態ではキレイにするという目標は達成できていませんね。
会社での会議も会議すること(話し合う)ことが目的になってしまって、本来の目的である問題の解決や決議に至らないことがしばしばあります。
今目の前に起こっている出来事や今後の予定の中で自ら優先したいことを信念として持って最優先していくことが大切です。
そして『7つの習慣』ではここまでの3つの習慣を、自己を精錬する段階として「私的成功の領域」とまとめています。
Win-Winを考える
第4の習慣は『Win-Winを考える』です。
『Win-Win』とは人間関係においてお互いの利益になる結果を目指すことを前提とした考え方のことを言います。
また合わせて『No Deal』という考え方もあり、これは思いつく解決策などがWin-Winにならない(どちらかが妥協または損してしまう)のであれば、無理にその方法で押し進めないというものです。
そしてWin-Winの達成は、
- 自身の人格の充実
- 互いの信頼関係が強く結ばれている
- 双方の合意がなされ実行協力が成立している
- 関係を継続する仕組みが円滑に機能している
- 結果に至るための望ましい過程を辿っている
という5つの柱によって支えられています。
またこの柱も第1〜第3の習慣によって磨かれた自身の人格がその軸となることが要点となります。
まず理解に徹し、そして理解される
第4の習慣は『まず理解に徹し、そして理解される』です。
ここでは相手のことを理解するための傾聴方法について解説されています。
多くの人は、自身の価値観を通して相手も同じような価値観を持っている前提で話を進めてしまいます。
相手と自分の考え方や価値観が違うのに自分だったらこうするなどといった意見を押し付けてしまい、相手の立場で相手の話を聞くことができていません。
本書では「共感による傾聴」の上達のために下記の4ステップを紹介している。
- 話の中身(キーワード)を繰り返す。
- 話の内容を自分の言葉に置き換えて言い直す。
- 「楽しいね」「つらいね」など相手の感情を自分の言葉で置き換えるあいづちを打つ。
- ②③を同時に行うことで信頼感が生まれる。
ただしこうしたスキルを使った傾聴は、「相手のことを理解したい」という誠意があってこそのものであることは大前提として理解しておく必要があります。
シナジーを創り出す
シナジーとは個別のものを合わせて個々の和よりも大きな成果を得ることです。
著者のコヴィー博士はこのシナジーを「人生において最も崇高な活動」としています。
相手との価値観や考え方の違いを尊重し価値を見出すことで、協力し合う際に妥協ではなく新たな成果が生まれたりします。
1+1が2ではなく3にも4にもなるシナジーを生み出すためには相手との深い信頼関係や忍耐力が必要なため、他の習慣と合わせて普段から意識して行動することが大切です。
刃を研ぐ
第7の習慣は「刃を研ぐ」です。
本書では体調(肉体)、観点(精神)、自律性(知性)、つながり(社会・情緒)の4つの側面でバランスよく自分を磨く時間をとる習慣としています。
肉体面では食事・休養・運動によって身体をメンテナンスし、精神面では心を落ち着けて自身の価値観をしっかりとみつめることが重要です。
そして知性面では知識を増やし情報選択・収集能力を身につけ、社会・情緒面では他人との関係を強化し心の平安を保つことを目指します。
この刃を研ぐ(自分磨き)がこれまでの第1~6の習慣とシナジーを生み、好循環に入って人生は前に進んでいきます。
習慣は人生を変える
今回は世界的名著『7つの習慣』のポイントを要約しました。
この7つを意識して日々を送れば確実に人間力アップにつながるとても学びが多い内容となっています。
『7つの習慣』はまんがでわかるシリーズも出版されていますので入門としてまずそちらから読んでみるのもおすすめです。
最後までお読みいただきありがとうございました。